今の会社に疑問はありますか?これからも迷いなく今の会社に勤め続けようと思えていますか?
仕事と会社の悩みは多々あると思います。迷いが出た時に読んでほしい一冊を紹介します。
北野唯我さんが書かれている本になります。
北野唯我さんは博報堂に入社し、その後はボストンのコンサルティンググループに入社、今はワンキャリアという転職ポータルサイトのを運営する会社の取締役をしている方です。
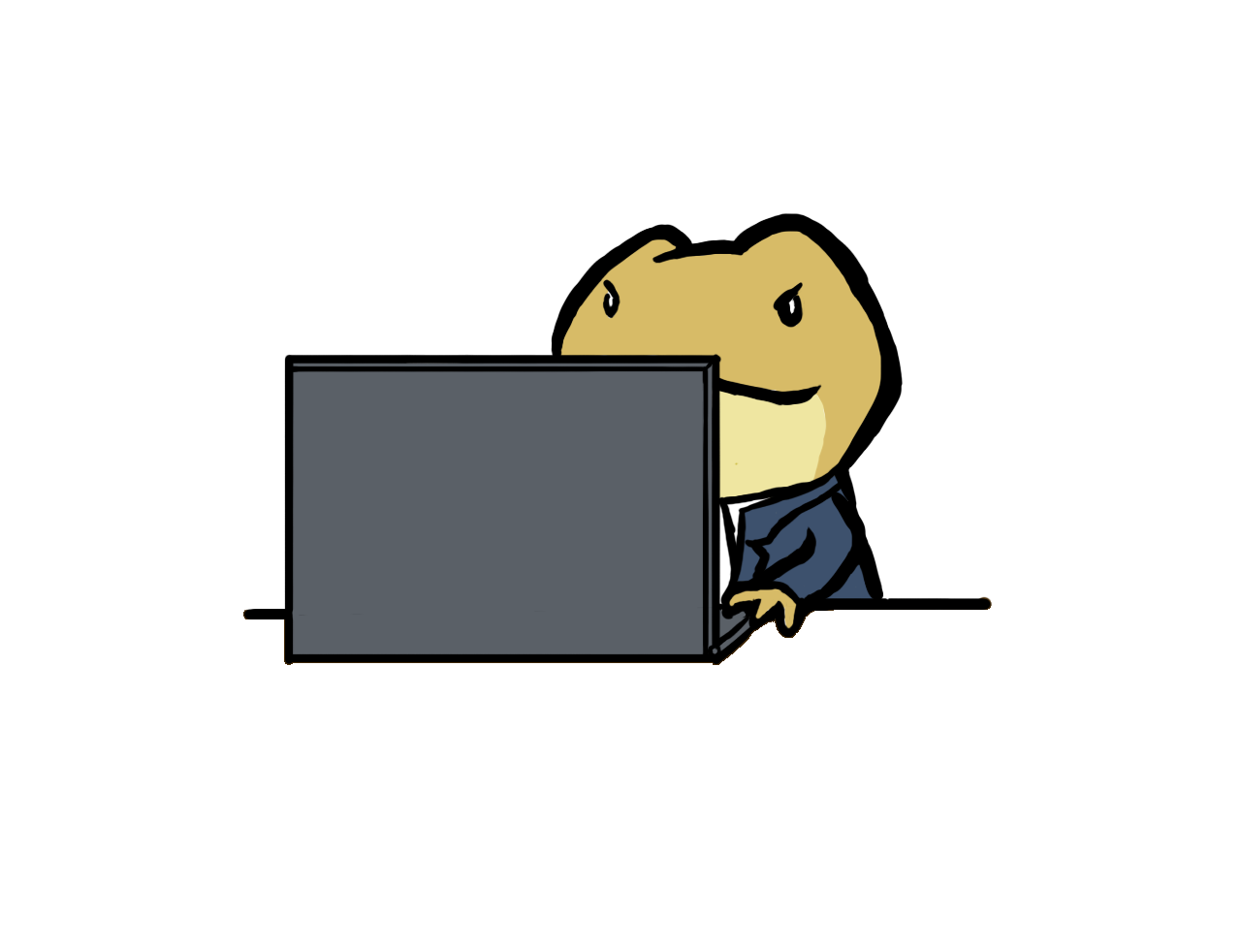 ヤモリン
ヤモリン働く人は読んでほしい
今後に役立つ本だよ
働く人全員が参考になる内容ですので、要点だけに絞っても1回にまとめることは出来ません。今回は「転職の思考法」を3回に分けて解説していきます。

- 今の会社に疑問がある人
- 仕事内容に迷っている人
- 転職を考えている人
マーケットバリューとは何か
これは直訳すると「市場価値」です。
言い方は悪いですが、サラリーマンは労働力という一つの商品と仮定したときに、その自分の労働力という商品価値がどれだけあるか理解しましょう。
理解するだけではなく、それを日々高めていきましょうということが書かれています。
マーケットバリューの高い人は市場価値が高いので色々な会社が欲しがるでしょう。
これにより今勤めている会社が急に倒産したとしても、「次に行こう」と思って簡単に転職が出来る訳です。
一方、マーケットバリューが低いと会社が倒産すると、「あ~終わった」と自分も終了していまいます。
今年のコロナウイルスもそうですが、会社自体のスマート化はこれからも進んでいくことでしょう。自分の周りがスマート化になりつつあることに気付いているのではないでしょうか。
社会全体が厳しくてもマーケットバリューが高ければ状況がどうであれ、くいっぱぐれることがなくなるのです。
ですから自分のマーケットバリューがあるのかないのか、どう高めていくかを理解できれば今後に活かせるようになります。

マーケットバリューの軸は3つ存在する
- 技術資産
スキルを持っている人
資格を持っている人や特殊な能力を持っている人 - 人的資産
コミュニケーション能力の高い人
誰とでも仲良くなれるだけでなく、個人あてにきちんと仕事が返ってくる為のコミュニケーション能力を持っている人 - 業界の生産性
自分の所属している業界がどれくらい儲かるかが自分のマーケットバリューにも繋がる
例を挙げると給料の高い低いは業界がどれだけ儲かっているかで大半が決まってしまうという事
労働市場での価値を上げたいなら儲かっている業界か急成長している業界に所属すること
これを考えてもらえれば自分のマーケットバリューを見つめてもらえると思います。では今後に何をしてマーケットバリューを上げられるのかという事になりますね。
マーケットバリューを上げる考え方を次項で説明します。
マーケットバリューの高い人は上司ではなく、マーケットを見て仕事をしている
マーケットバリューのある人とない人の決定的な違いは上司を見て仕事をしているか、お客さんを見て仕事をしているかの違いです。
詳しく言うと、マーケットバリューのない人は社内に向かった仕事をしています。
上司や同僚や他部署に褒められようと仕事をしたり、最低限怒られないように仕事をしているのです。
こういう人は残念ながらマーケットバリューは上がっていきません。
一方でマーケットバリューの高い人は、お客さんやマーケットを見て仕事をしています。
例えばテレビを作っている会社の開発に所属しているとしたら、社長や同じ会社の人が喜ぶようなテレビを開発しているようではマーケットバリューは上がりません。
逆にお客さんや市場を調査して求められている物に対して供給しようと考えるのであれば、あなたのマーケットバリューはどんどん上がっていきます。
ですが、不思議とお客さんやマーケットを意識して仕事をすると社内で批判や摩擦が起こりやすくなってしまうのです。
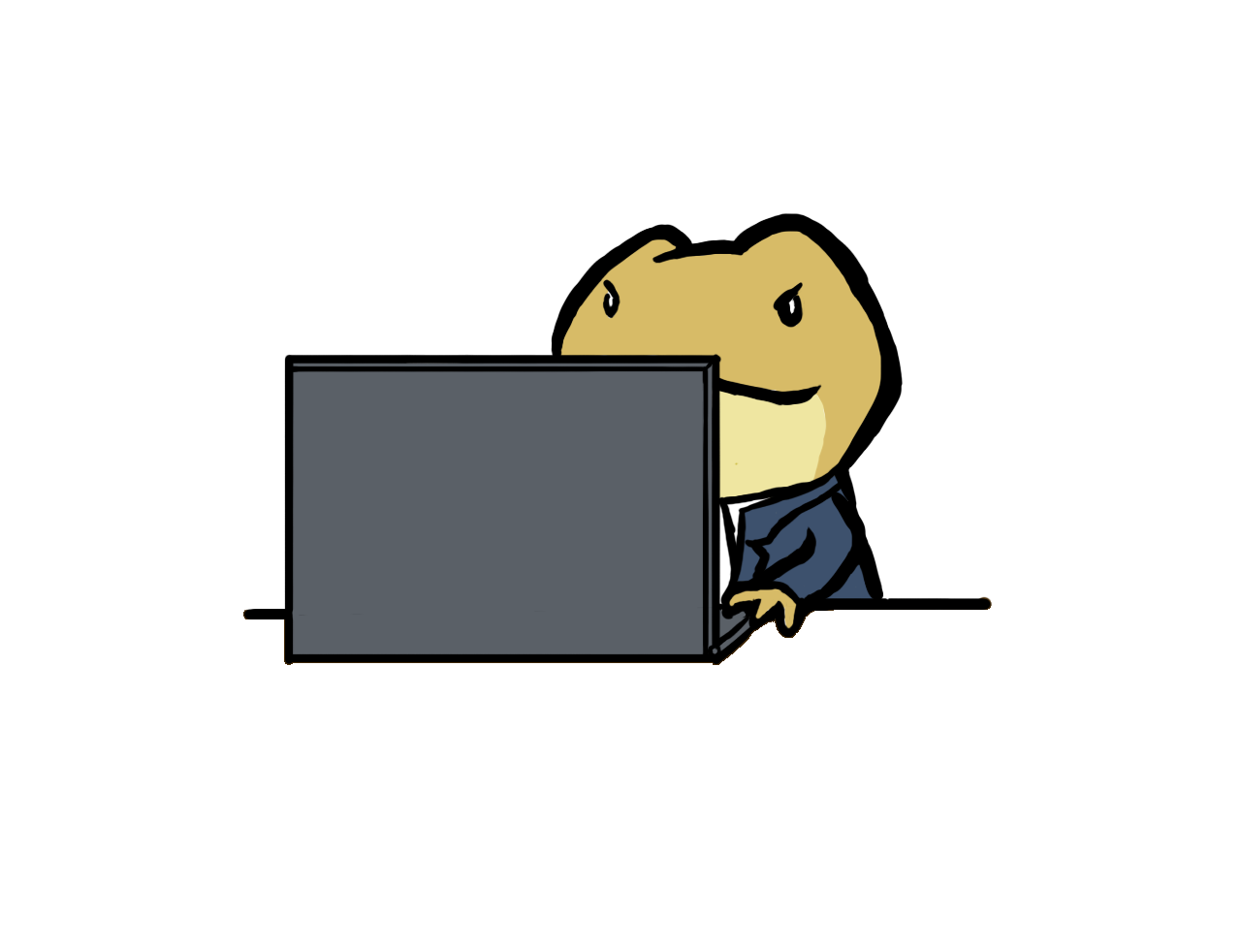 ヤモリン
ヤモリンどの会社でも起こる摩擦だね
乗り越えるべき壁なんだよ
偉い人や古い人から「勝手なことするな」や「やり方を変えないでくれ」などと言われて正直きつくなる事があります。
ですが、摩擦を乗り越えながらお客さんが求めるものを提供することで自分のマーケットバリューはどんどん高まっていくのです。
お客さんの事をみて仕事をすることはメチャクチャ大事ですが、約9割のサラリーマンは出来ていないことなのです。
それは、お客さんと社内の人とで言葉を交わす時間が違うことに原因があります。
お客さんと話をするより、社内で会話をする時間の方が長いはずですから社内の声に影響を受けやすくなるのです。
そして社内の声に対して仕事をする方が摩擦が起きにくいですから楽は楽なんです。
社内の製品に対してユーザーはあまり怒ってきませんが、社内の人は怒ってきます。
社内の人を気にして仕事をしてしまうと楽ですが、自分のマーケットバリューはどんどん下がってしまうでしょう。
社内の人だけを喜ばせても喜ぶのはユーザーではないので、自分もその会社でしか生きていけなくなってしまうのです。
お客さんが欲しがる製品が作れる人やアイデアを出せる人はどの会社でも同じ事をしますから、今の会社に囚われること無く進んで行けるようになります。
どこに目を向けるかでマーケットバリューを高めることが出来るのです。
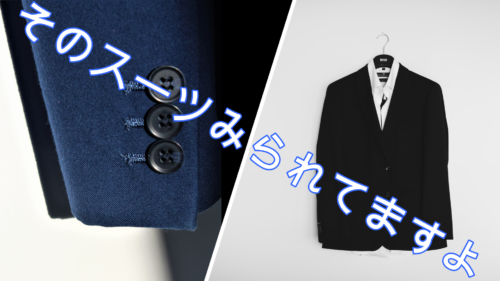
「転職の思考法」1のまとめ
今回は社内の摩擦などがあるとは思いますが、マーケットを見て仕事をして自分のマーケットバリューを上げましょうという話をしました。
本にはほかにも書かれていますが、私が一番本質的だと感じた1点をここでは紹介しました。
他の内容も気になる方は、是非一度、本を読んでみてください。
このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法
この本の他の内容も随時書きます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
おわり

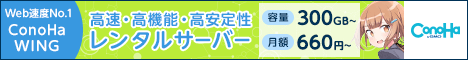


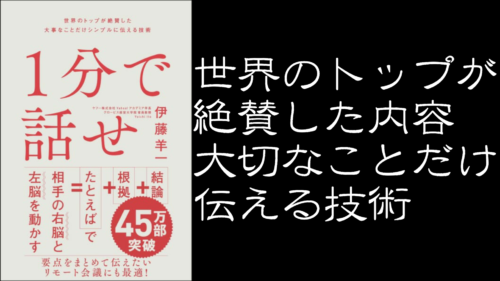
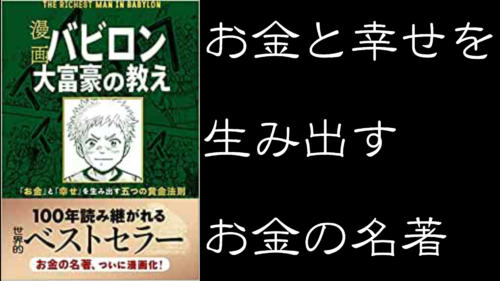





コメント