私の子供は社会人になってから、うつ病と診断されました。
親としては「なんできちんと出来ないんだろう」とか「何を落ち込んでいるんだろう」などと本人の気持ちより、親としての気持ちを優先してイライラしてしまいます。
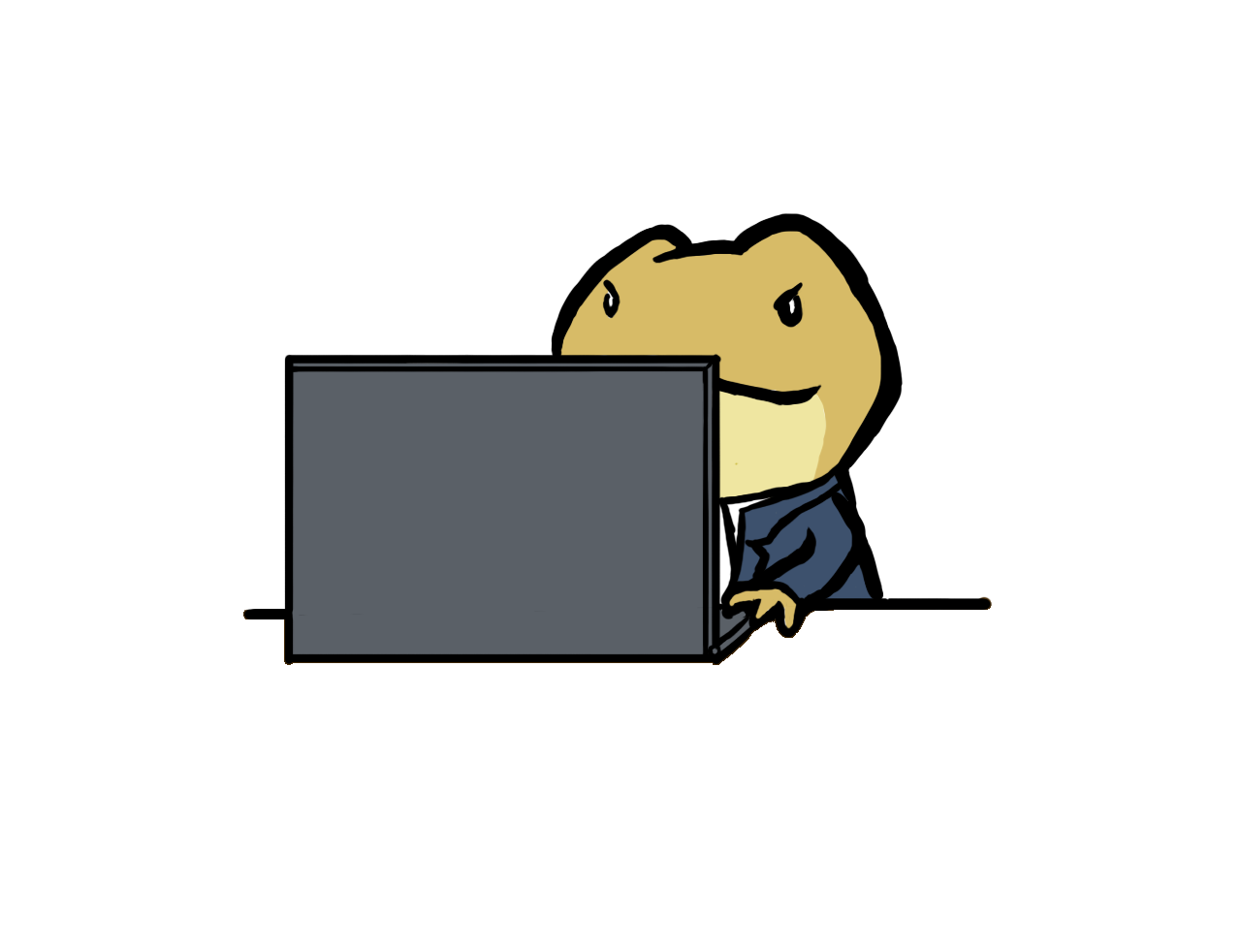 ヤモリン
ヤモリン本当に最初は何が何だか分からなかったよ
実は、親として良かれと思ってしていることが子供の負担になっているケースもあるのです。
今回は私の子供がうつ病と診断された日までの経緯と親として感じた大切な部分のお話をしていきます。
同じように子供がうつ病だと診断されて悩んでいる方はこの続きの記事をこちらからどうぞ。
自分だけで悩まずに相談をしましょう。多くの方がクリニックに通うところを見られたくないはずです。オンラインクリニックを活用することでメンタルの状態が整いますよ。
この記事を最後まで読むことで、子供が本当は悩んでいる可能性に早く気付けるようになります。
・子供の様子が最近おかしいと思っている方
・子供が落ち込んでいるように見えている方
・子供が学校や会社を休みがちになっている方
子供の変化に早く気付いて、優しく見守る気持ちを身につけましょう。
私の子供がうつ病と診断されるまでの経緯について
私にはうつ病と診断された子供がいます。
私自身が経験した「何かおかしいな」が「うつ病かぁ」に変わるまでの経緯をお話しします。
- 会社や学校に行ったり行かなかったりの状態になる
↓ - 会社や学校から心療内科での診断を打診される
↓ - 子供と話をして改心してくれればと思い、子供と話をする
↓ - 子供の行動が嘘を伴うようになる
↓ - 心療内科で診断し「うつ病」と診断される
順を追って説明していきますので、自身の子供に当てはめていただけると幸いです。
会社や学校に行ったり行かなかったりの状態になる
私の子供の場合を紹介するので、症状自体に個人差があると思います。
まず、「おなかがいたい」などを理由に会社や学校に行ったり行かなかったりの状態になりました。
最初は内科の受診をして薬を出してもらいましたが、子供の行動は変わりませんでした。
この時点では体調不良を信じている状態なので、「まったく!困ったものだ」と思っているだけです。
会社や学校から心療内科での診断を打診される
行ったり行かなかったりの行動は変わらず、「薬は飲んでいる?」などの確認と「行かないと行きづらくなるよ」などのアドバイスをしましたが、たぶん本人には負担だったのだと思います。
会社や学校は「来ない」のではなく「来れない」のではないかと感じていたらしく、本人に心療内科の受診をすすめたそうです。
このときは、親として「うちの子に限って心療内科にいくようなことはないはず」と思い、本人の心の弱さを説いている状態でした。
子供と話をして改心してくれればと思い、子供と話をする
心療内科の受診をすすめられたことは本人から聞きました。しかし親としては「うちの子供が心療内科なんて・・・」と思う部分があり、自分たちで何とかしたいと思いました。
本人と話をして、なんで「行かないのか」を聞いてみました。
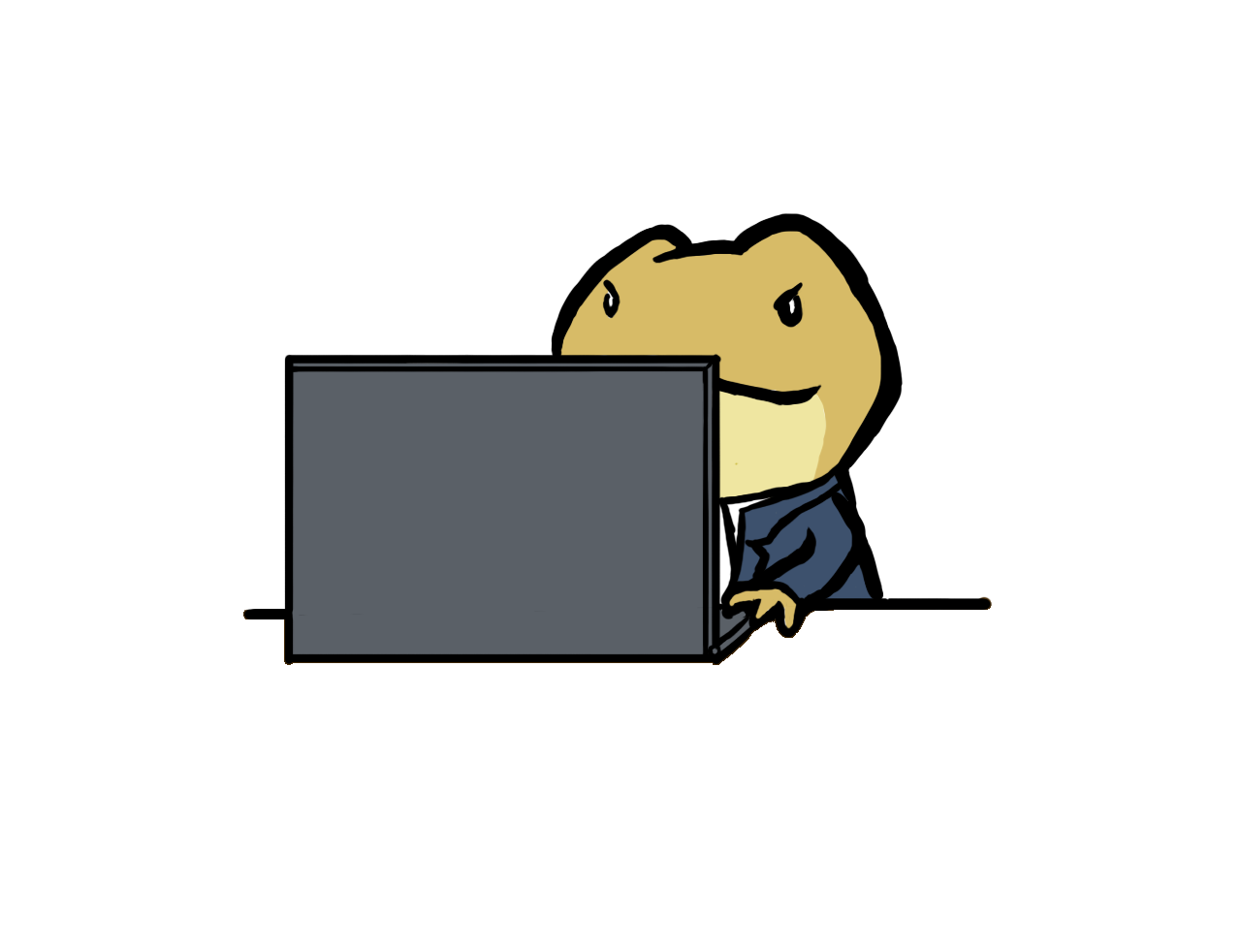 ヤモリン
ヤモリン向き合うことが大切なんだよね
本人は恋愛で当時の相手とお別れしたことで意気消沈し、やる気が起きないことや、やる気が起きないのに親からはプレッシャーを掛けられることで悩んでいたのです。
私は今まで自分が良いと思っていた部分が逆に負担になっていたことを知り、ショックを受けた半面、親としてしてあげなければいけないことを考えるようになったのです。
本人が望むようにしてあげたいと思い、本人の希望にそった対応をすることにしました。
子供の行動が嘘を伴うようになる
子供と話をして、翌日から子供は「行ってきます」と朝から規則正しい生活をしているように見えました。
しかし、じっさいの行動は変わっていませんでした。それは会社や学校からの連絡で分かりました。結果、子供は「心配を掛けてはいけない」と思い出掛けていただけだったのです。
嘘をつかなければいけないように親の私が追い込んでしまったのではないかと思いました。
しかし、周りの人が気をつかうように本人も周りに対して気をつかっているのです。これは親や家族だけで考えるのは難しいと感じ、心療内科での受診を決心する決定打になりました。
心療内科で診断し「うつ病」と診断される
子供が嘘をつくようになると、嘘を嘘で重ねていくようになります。
親の感情が先走る対応では子供を追いつめることになると思い心療内科の受診を本人にすすめて受診しました。
心療内科での診断は「うつ病」と診断されました。
最初は体調不良だったと思い、子供への対応をしていましたし、まさか身内で「うつ病」と診断されるひとが出るとは思ってもいなかったので一瞬はショックでしたが、思い返すと子供がしていた行動は「うつ病」の人に見られる症状だと聞きました。
今までとは投げかける言葉と行動を変えていかなければいけないと感じた瞬間だったのです。
頑張ってほしくても「がんばれ!」と言わないことの大切さ
私たち親は、子供に少なからず「がんばってほしい」と思っている部分があります。
「自分と同じ思いをさせたくない」や「お金で苦労してほしくない」など、思いはさまざまですが少しでも良い人生を後に送ってほしい思いから「がんばってほしい」と思ってしまいがちです。
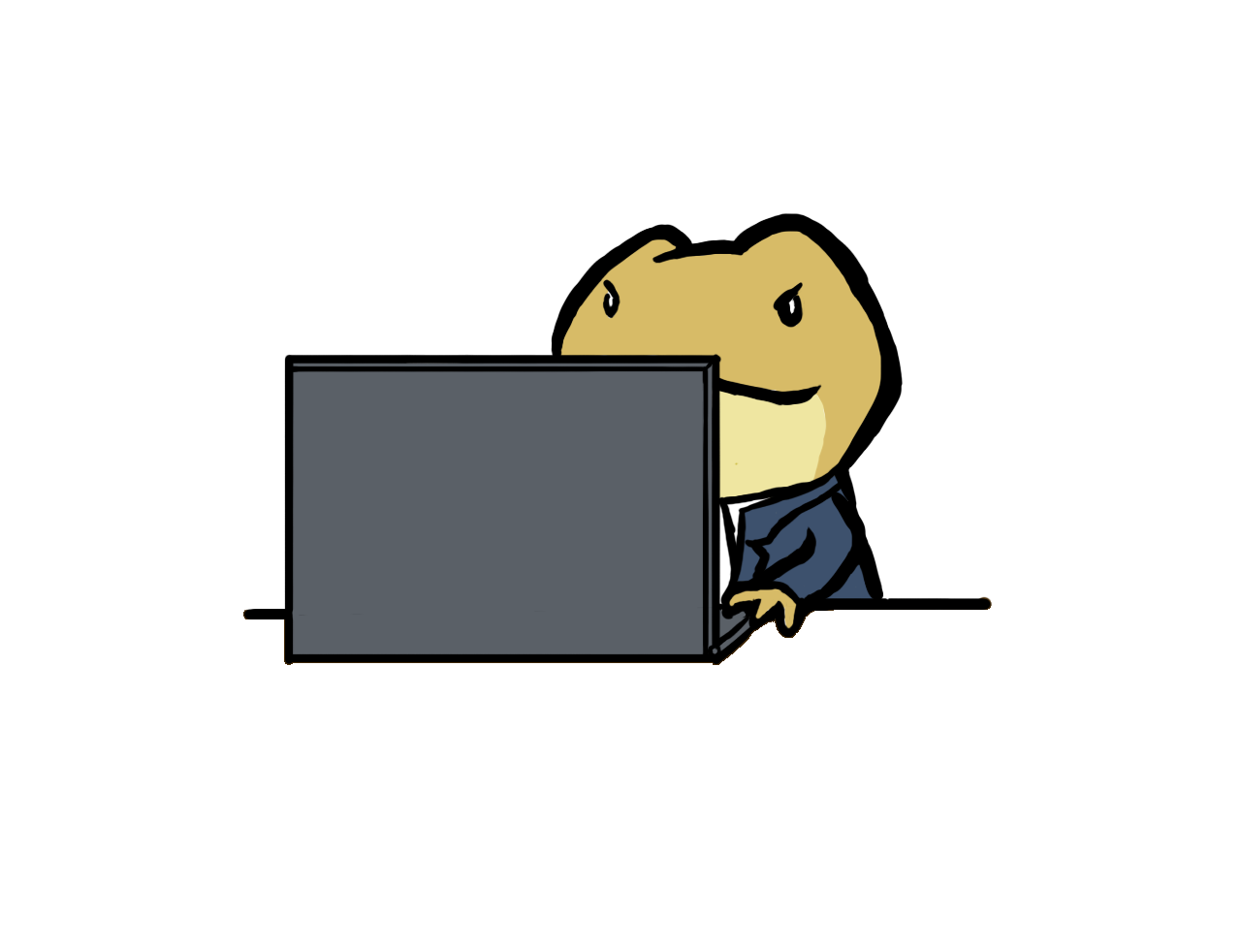 ヤモリン
ヤモリンがんばれ!が逆効果なときもあるよ
子供が「うつ病」と診断を受けて気付いたのですが、「がんばれ!」という応援が本人にとってはプレッシャーになってしまうケースもあります。
私は子供を通して「がんばれ」と言わないことが大切な場合もあることを理解しました。「がんばれ」と言われたくないケースは子供の意見を聞きましたので下記にて確認ください。
①気分があがっていないのに「がんばれ」の言葉でさらに気分が下がる
②「がんばれ」と言われることが頑張りを強要されているように聞こえる
③本人も頑張りたい気持ちはあるので、「がんばれ」の言葉は「うるさい」と感じる
世代が変わるだけで考え方も変わりますが、「本人を尊重」という言葉が強くなっていますので理解していくしかないでしょう。
「がんばれ」と言われたくないケースを子供の意見を参考に項目ごとに説明します。
①気分があがっていないのに「がんばれ」の言葉でさらに気分が下がる
がんばろうと思っているときの声掛けに関しては本人も嫌ではないと言ってましたが、がんばろうと思っていないときに言われると「なんで?」と思うらしいです。
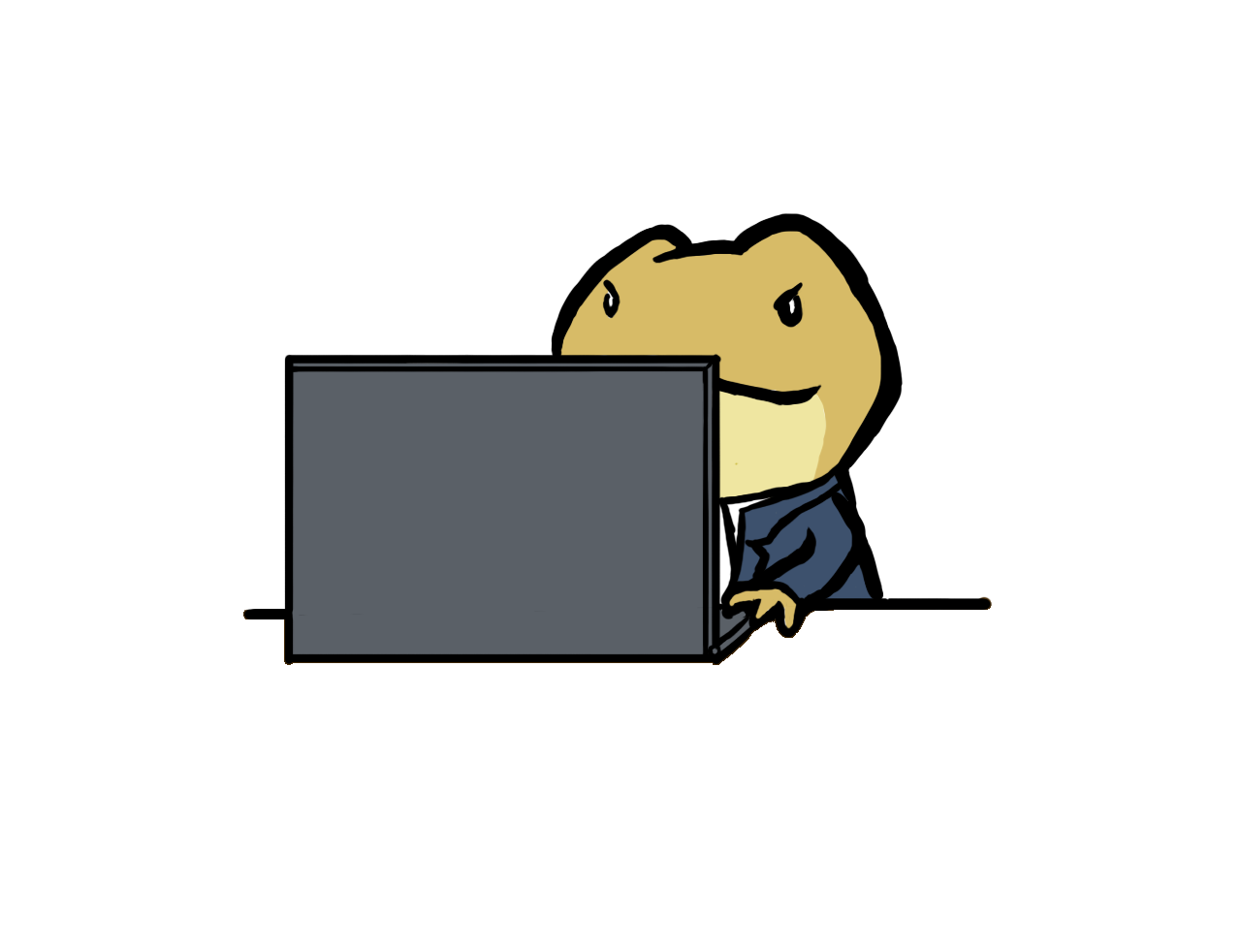 ヤモリン
ヤモリン応援したいという気持ちが迷惑らしい
そして「がんばれ」という言葉が気分を下げる逆効果になってしまうと言われました。
親として当たり前のように言われた「ばんばれ」は使いどころがむずかしい言葉になってしまったのです。
②「がんばれ」と言われることが頑張りを強要されているように聞こえる
親としては応援のつもりで言っている「がんばれ」の言葉ですが、子供からしてみると「がんばる」ことを強要されているように聞こえるそうです。
「がんばりたいから学校に行ったり仕事にいったりしているわけではない」と言われました。
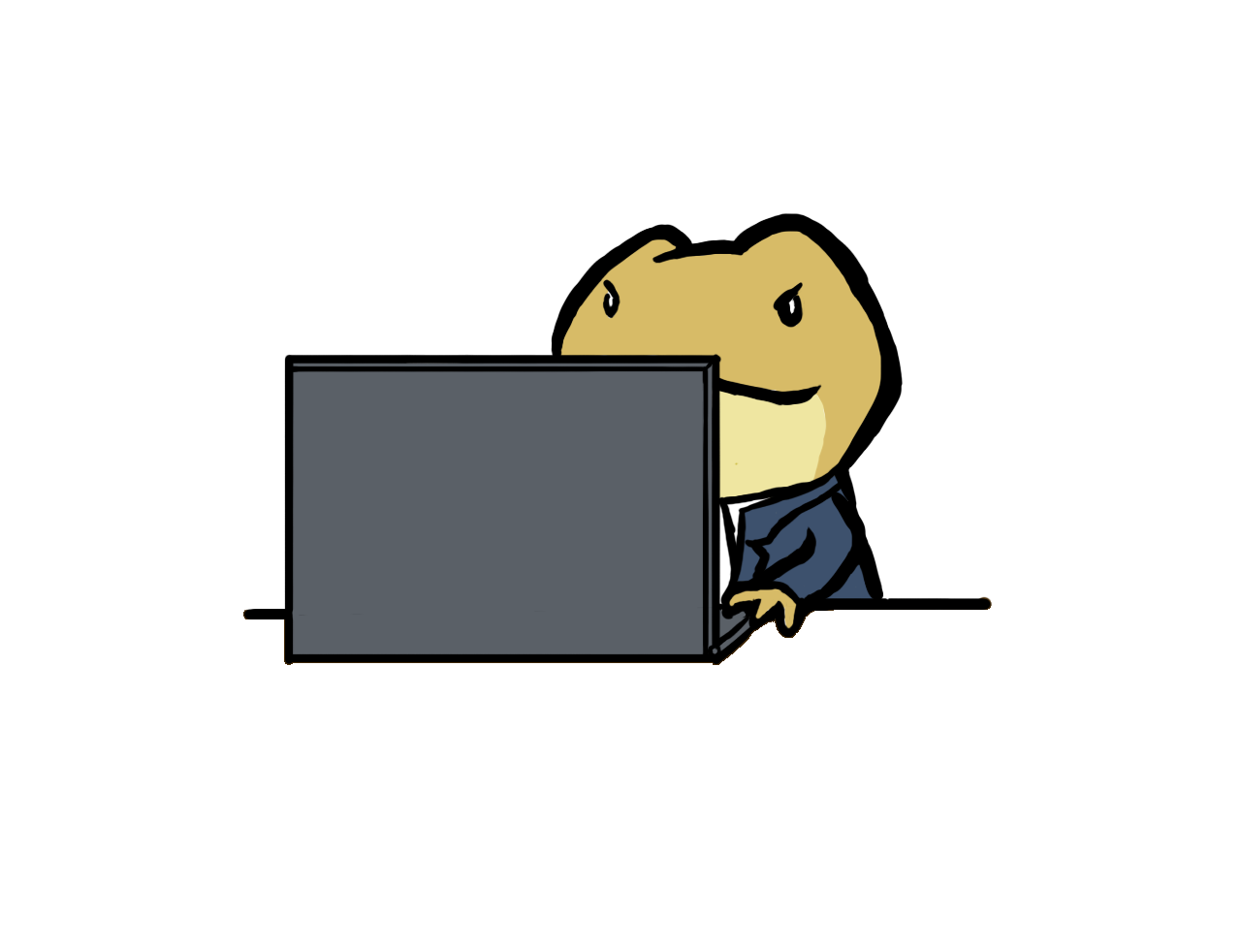 ヤモリン
ヤモリンこれって本当にむずかしい問題!!
がんばらなきゃと思っているときはあるし、言ってもらわなくてもがんばるから、そっと見守っているだけでいいそうです。
親として先走ってしまう部分はあると思いますが、そっと見守る思いやりが必要でしょう。
③本人も頑張りたい気持ちはあるので、「がんばれ」の言葉は「うるさい」と感じる
私の親としての気持ちは、子供が成長していく過程の中で苦労をしてほしくないと思っています。
最初にいろいろなことを経験し吸収して後に役立てれば少しでも苦労する場面が減るはずと思い、「がんばれ」の言葉を出していました。
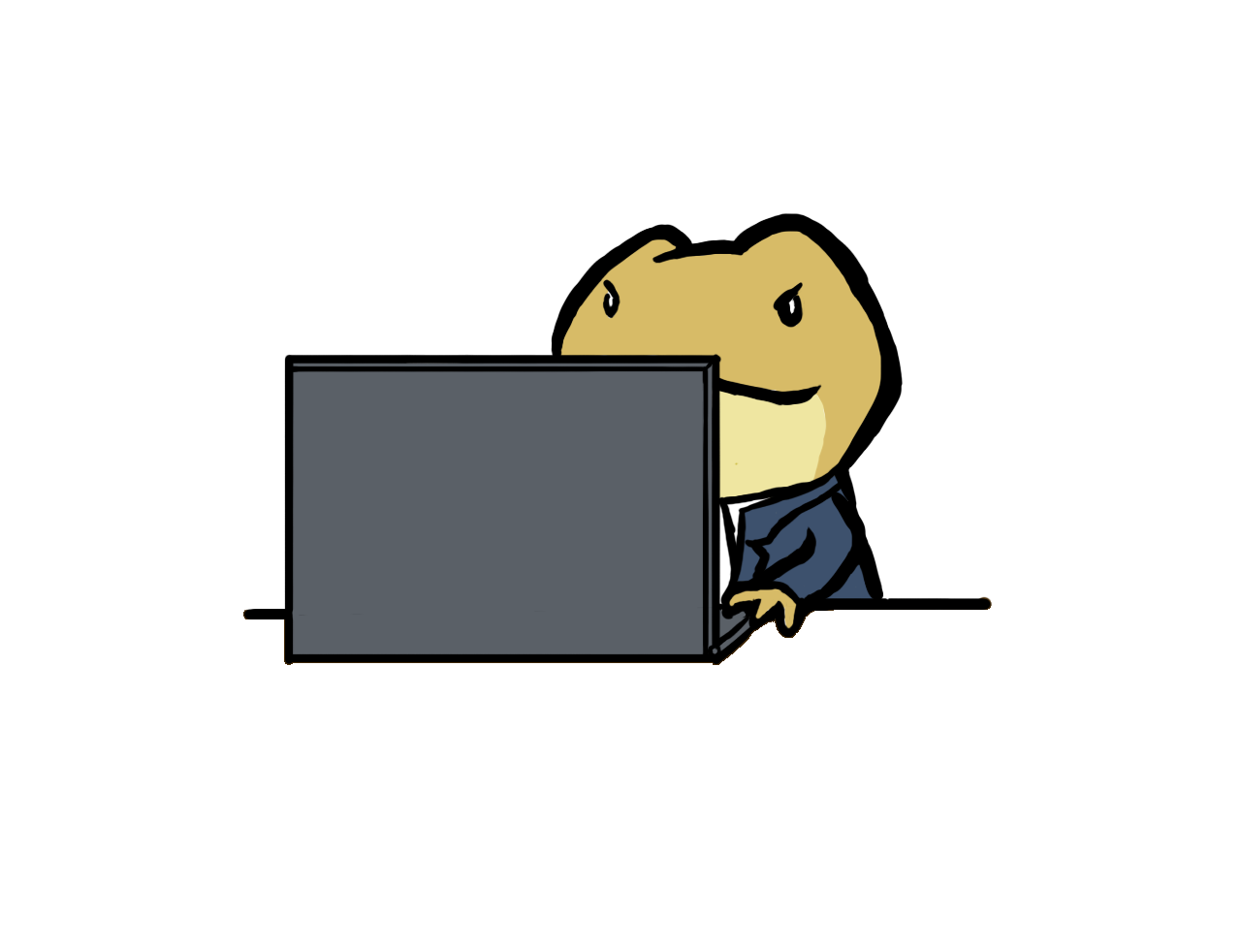 ヤモリン
ヤモリン同じ思いの方いるのでは?
親だと、「もうちょっとがんばれ」「ここの部分をがんばれ」「もっとがんばらないと!」などの声をかけていませんか。
がんばろうと思っているときに「がんばれ」の言葉は「うるさい」と感じてしまうらしいです。なぜなら思っていることに輪をかけて言われている状況だからです。
少なからず、親の言葉を「うるさい」と感じたことは1度や2度ではないはずです。知らないうちに自分が同じことをしてしまっていると子供に気付かされました。
不安を感じて頻繁におなかが痛くなるらしい
不安を感じる(プレッシャーのかかる状態)になると、おなかが痛くなった経験は多くの人が体験しているでしょう。
私も大勢の前で話さなければいけなかったり、大事な決断を迫られるときは今でもおなかが痛くなります。
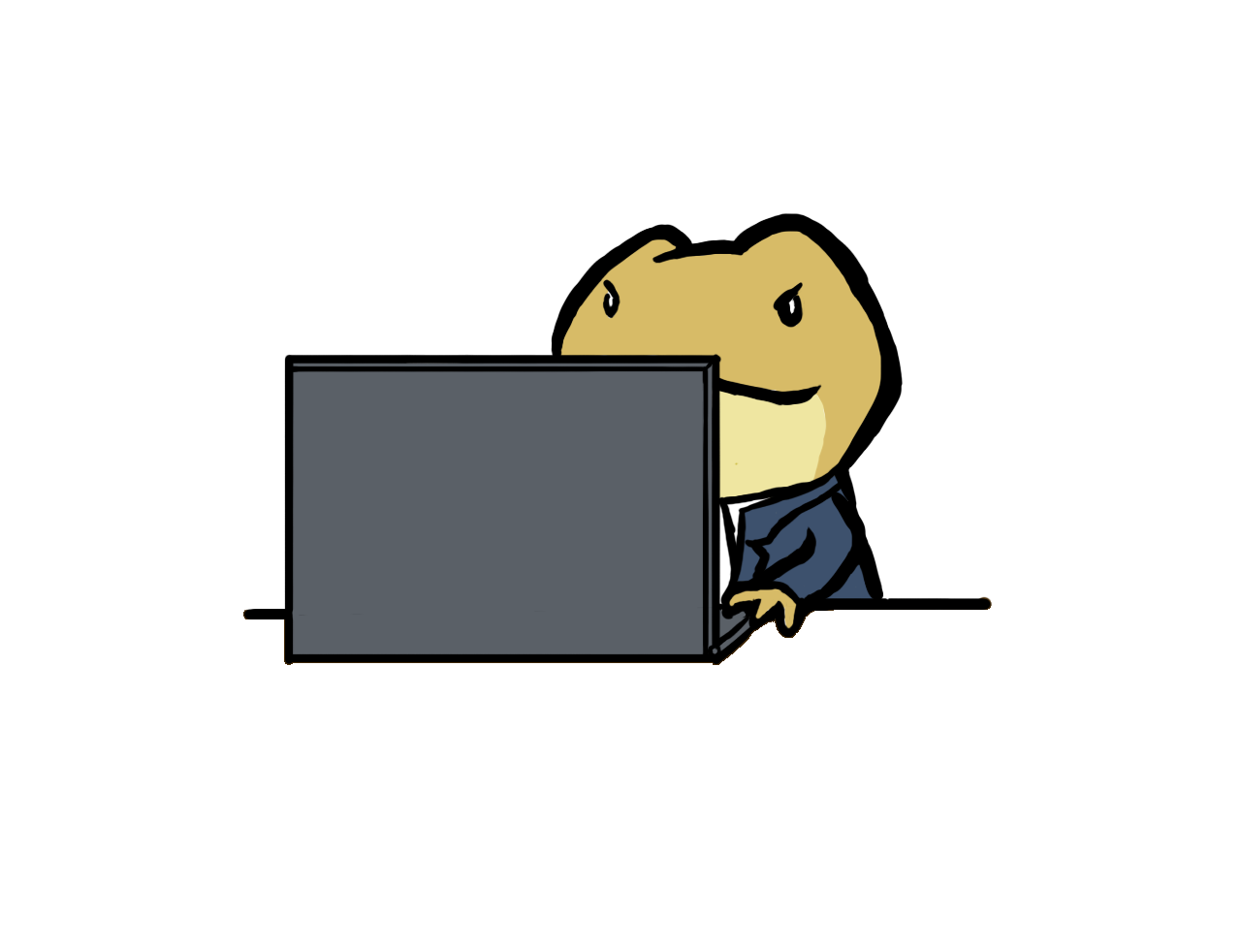 ヤモリン
ヤモリン何歳になっても気持ちは弱いままなのよ
不安と向き合っていられるうちは耐えられるプレッシャーだということになりますが、不安を感じ頻繁におなかが痛くなるとトイレにいる時間だけが長くなり戻りづらい状態になってしまいます。
頻繁にトイレに行き、どんどん居づらい状態にしていまい結局は行かなくなってしまうのです。
私の子供が実際に話した内容からお伝えしているので、医学的な部分ではありませんが、本人の志向と行動はありのままお伝えしています。
けっきょく子供は見捨てられない
私は子供がうつのなりかけだったときから「なんでちゃんと行ってくれないのか?」「周りはやれているのだろう?」「らくをしているのでは?」と考えていました。
自分勝手な行動に見えていたがゆえに、勝手にすればいいと感じた部分もあります。
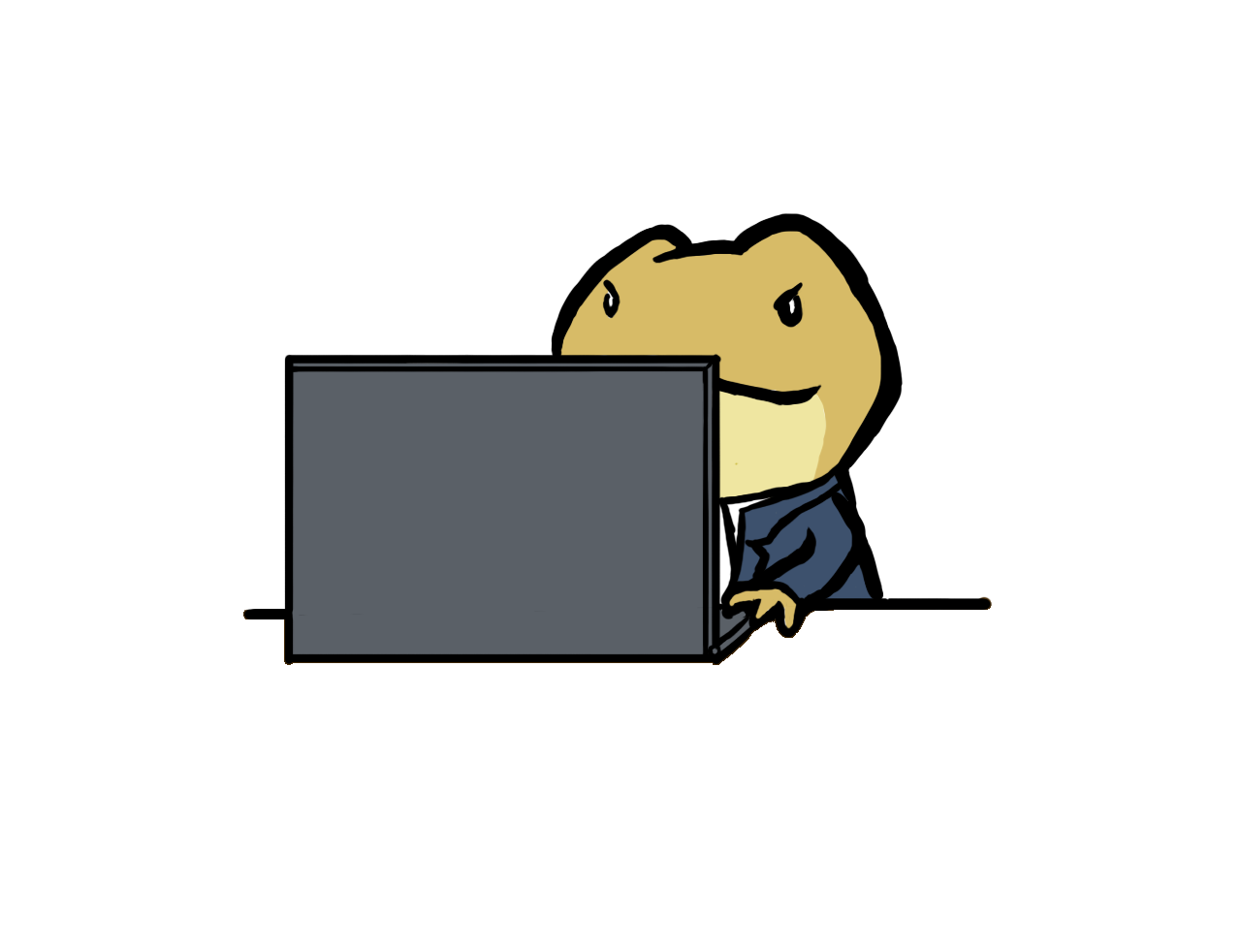 ヤモリン
ヤモリンほんとうに悩ましいんだよね
それでも、子供を見捨てることはできないと思いました。自分の出来ていることが当たり前だと思わないことが重要です。
人それぞれの個性があり、集団で集まる集合体が社会ですからいろいろな考えを持ち、いろいろな思いがあって当然なのです。
一過性の病気と言われているのと、うつ病と診断される人の多さを目の当たりにして、今は見守っていくことを決めました。
同じような思いをしている方、一緒に向かい合っていきましょう。
おわり

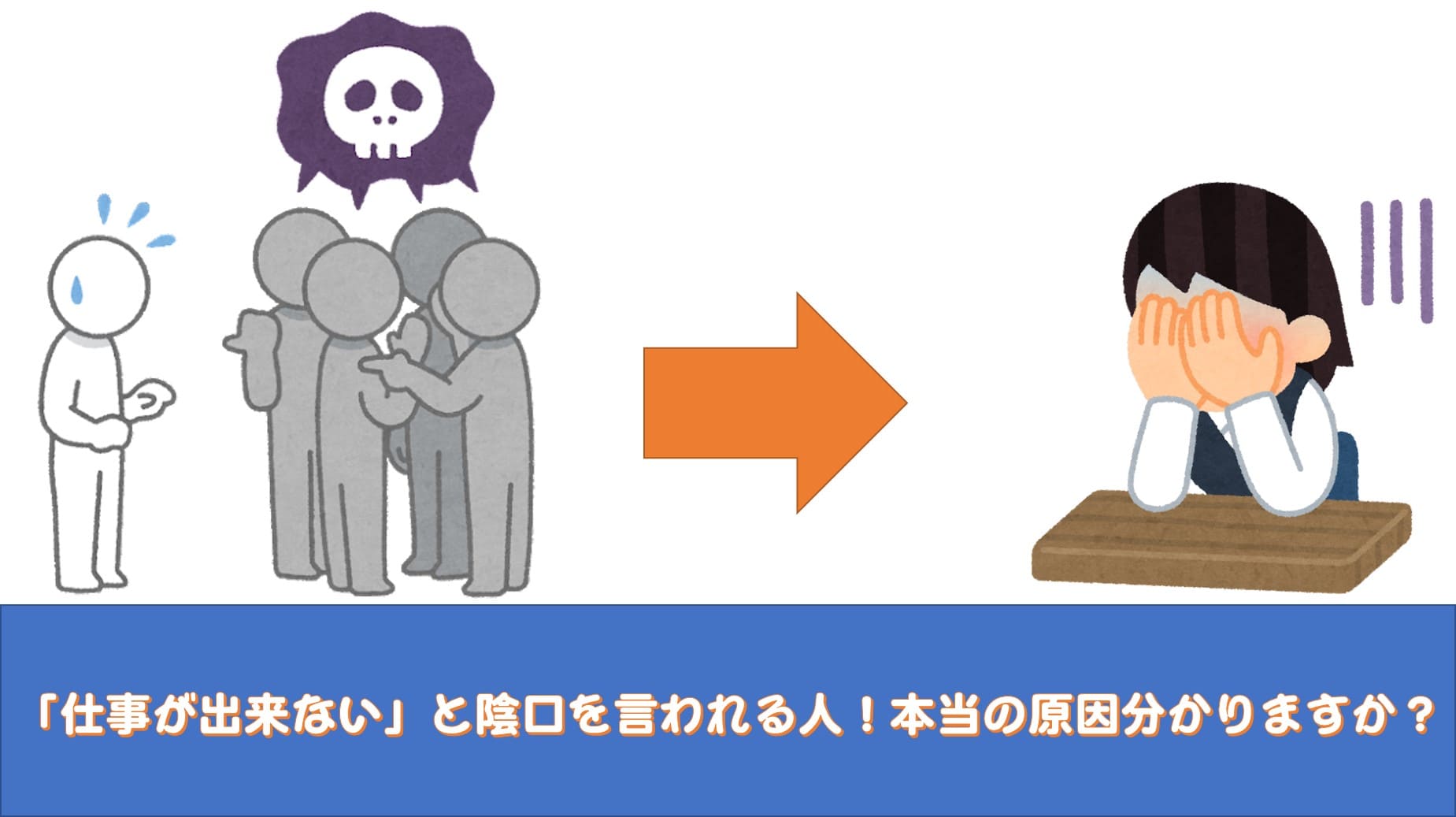








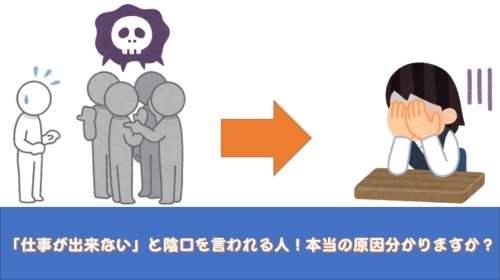
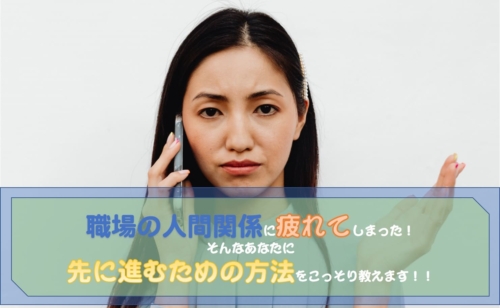
コメント